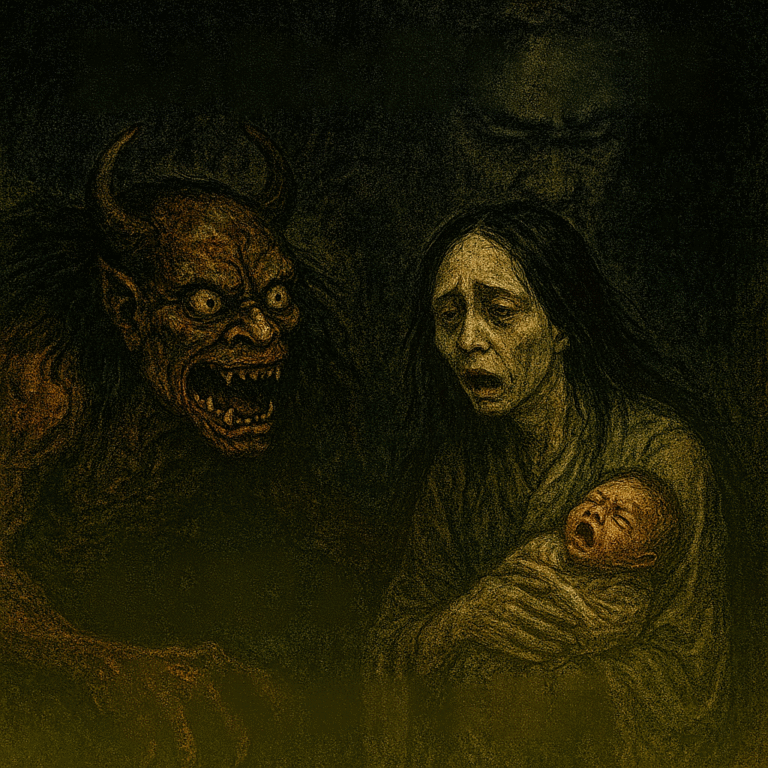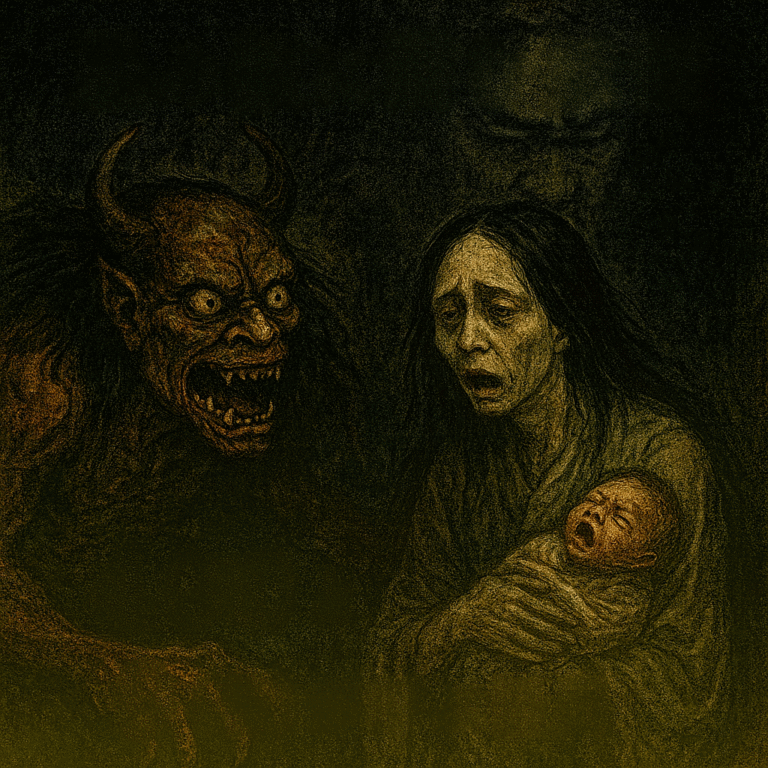雨戸を叩く誰か
解説
日本の文化には、特定の数字に対する忌みが色濃く存在する。特に「4」と「9」は、発音がそれぞれ「死」と「苦」に似ているため、忌避される傾向が強い。これらの数字は、日常生活においても縁起の悪いものとされ、例えば葬儀の場面や不吉な出来事に結びつけられることが多い。
妖怪や様々な伝承とも深く結びつく「忌み数」は、人々の心に恐怖を植え付け、その存在を意識させる。悪い事象の象徴として、これらの数字は注意を引く存在となり、その背後には多くの人々の恐れや不安が潜んでいる。和風怪談において、このような不可解な恐れが物語の根幹を成し、その余韻を深めるのだ。
怪談
梅雨の季節。古びた旅館に、宿泊客がやってきた。薄暗い廊下に、雨音が響く。彼は一室に通され、温かいお茶を飲みながら、静寂を楽しんでいた。しかし、いつしかその静けさは壊される。
廊下の先から、雨戸を叩く音が聞こえてきた。最初は小さな音だったが、次第にそのリズムは強くなり、まるで誰かが外から迫ってくるようだった。宿泊客は気にしないように努めたが、音は止むことなく続く。
「それ、雨戸が傷んでいるんだよ」と仲居が通りかかり、不敵な笑みを浮かべた。「たまに、そういうこともあるから」彼の言葉には妙な余韻があった。宿泊客は、思わず目を細めた。確かに、旅館の老朽化が進んでいるせいかもしれない。
しかし、音はますます大きくなり、まるで何かが迫ってくるようだった。横目で見る廊下の影は、どこか濃く、暗い。宿泊客は、心のどこかで不安が広がるのを感じた。そんな折、突然、叩く音が止んだ。
静寂が戻り、彼は安堵の息をついた。だが、その安堵も束の間、視界の隅に何かが動くのを感じた。振り向くと、なにもない。廊下は闇に包まれており、ただ静まり返るだけだった。再び、音がし始める。
今度の叩き方は、まるで繰り返される意図のようだった。心臓が速く鼓動する。何かが、ここにいる。彼は耐えきれず、部屋を飛び出して廊下を駆け抜けた。だが、そこに待っていたのは無情な闇だけだった。
彼は、途中で出会った仲居の顔を思い出した。「たまに、そういうこともある」と言っていた。宿泊客は、自らの声に恐れながらも、外に出る勇気を持とうとした。けれど、彼の目の前に広がるのは、濡れた床と雨音だけ。
その瞬間、もう一度、雨戸を叩く音が響いた。今度は近くで、真上から。宿泊客は立ち尽くした。雨音に混じる、異なるリズム。その正体が、恐ろしいほどに近くなっているのを感じた。声も出せない。彼は振り返るが、廊下には誰もいない。
背筋が凍る。再び静寂が訪れたとき、彼の耳元にささやく声が聞こえた。「4時、9分。待っているよ…」それは友人の声でも、仲居の声でもなかった。彼はその場から逃げ出したくて堪らなかったが、全身が動かない。
時間が止まったかのように感じる。音は、再び雨音と混ざり、消えていく。どこからか響く不気味な笑い声が、廊下の奥から聞こえてきた。それが、彼の心に恐怖を植え付ける。
やがて、再び雨戸を叩く音が響き渡る。その音は、彼の記憶の奥底に沈み込んでいた数字の不吉さを思い起こさせた。宿泊客は、逃げることも叫ぶこともできないまま、闇の中に吸い込まれていく。
その後、彼が見たものは、誰も覚えていない。ほんの薄い違和感だけが、長い間、旅館の廊下に残されていた。