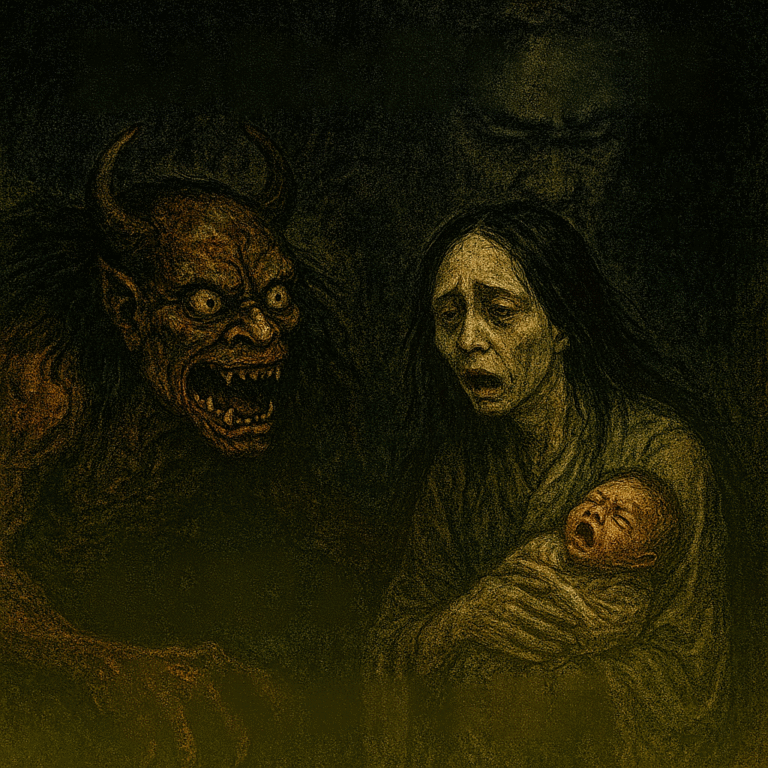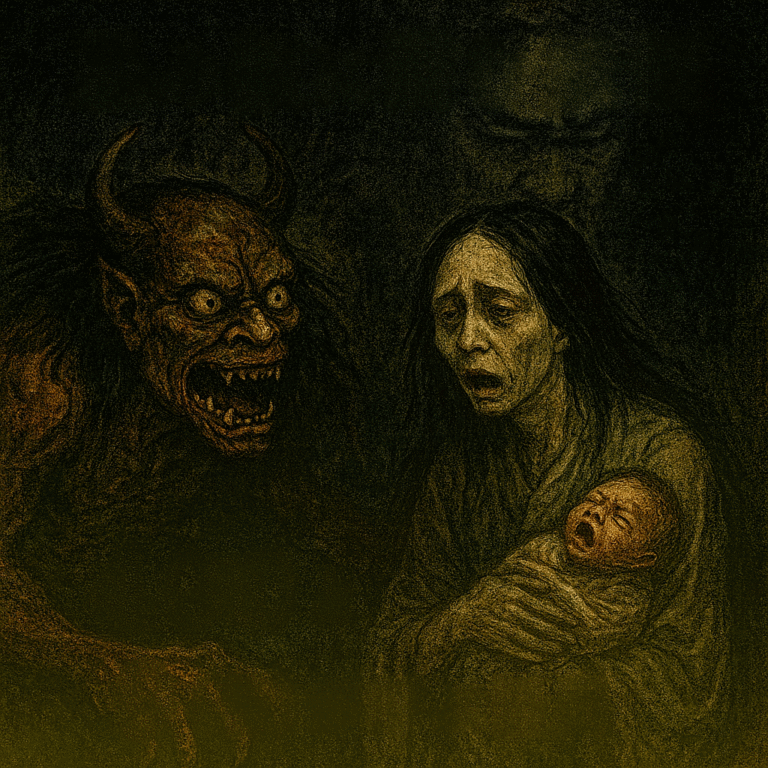廊下の尽きぬ灯
解説
日本文化において、数字の持つ意味は深く、時として人々の心に不安をもたらす。特に「4」と「9」は忌み数とされ、恐れられている。四は「死」、九は「苦」を連想させるため、特に葬式や不吉な場面では避けられる傾向にある。このような忌み数は、古来より様々な伝承や妖怪の物語に影響を与え、現代においても、例えば病院やホテルの部屋番号において顕著に見られる。
妖怪や幽霊は、このような数字にまつわる神秘性を利用し、人々の恐れを煽る存在として語られることが多い。例えば、住吉大社の「四つの橋」や、九尾の狐に象徴されるような、数にまつわる伝説は、常に人々の心に影を落とし続けている。こうした伝承は、単なる昔話に留まらず、現代の人々の意識に深く浸透しているのだ。
心の奥に潜む恐れは、時に日常の中でさえ影を落とす。たとえば、何気ない廊下を歩く際、ふと感じる気配や、目に見えない暗い隙間に意識が引き寄せられる。その瞬間こそが、文化に根ざした恐怖を呼び覚ますのだろう。
怪談
霧が深く立ち込める冬の夜、旅館の廊下は静まり返っていた。灯るはずの明かりは、やけに薄暗く、四方を囲む壁が、まるで視線を受け止めているように感じられる。進むにつれ、廊下の長さが永遠に思えてくる。その先に何が待つのか、何も見えないからこそ、想像は奔放に広がった。
一室に扉がある。手を伸ばし、ノブを回すと、重い音を奏でて開いた。中は酷く古びた様子で、薄暗い隙間から微かに光が漏れている。自分の影が揺れるのを感じながら、部屋の奥へと進む。
壁には、かつてここに住んでいたであろう人々の写真がかかっている。沈んだ表情、目はどこか虚ろで、今にも何かを訴えかけてくるようだ。しかし、どの顔にもアクセスできない影がある。笑っているはずの家族の笑顔も、どこか異様に感じられた。
ふと、視界の隅で動くものがあった。思わず振り返るが、そこには誰もいない。息を呑み、耳を澄ませる。廊下から真っ直ぐに響く足音。四人の声が、名を呼び合っているように聞こえた。
思わず心臓が高鳴る。その音が、まるで近づいているかのように感じられた。自分の名前も、淡く混じっていた。「逃げなきゃ!」と心の中で叫びながら、部屋を飛び出る。
廊下に戻り、冷たい壁に背を寄せて、何とか落ち着こうとした。しかし、その瞬間、影が自分の足元をぴったりと追いかける。無意識に走り始め、灯りの穢れた柔らかさを頼りに進む。
その時、何かが耳元で囁いた。「四つの足、九つの影」その言葉は、胸に重くのしかかり、全身が凍りついた。いつの間にか、廊下の尽きぬ灯に照らされた自分が、鏡の中で見知らぬ誰かと目が合っている。
一瞬の静寂に包まれ、ただ息をする音だけが響いた。視線がその影を追う。廊下の終わりが見えない。どこまでも続く、名も知れぬ恐怖が、闇の中にひそんでいるのを感じる。振り返ると、暗がりの中に無数の目が光っていた。
薄い光が進むほどに、居場所を求めて彷徨う影が、何かに怯え、何かを求めている。その背後に感じる温度は、冷たくも暖かいのか。ほんのりとした恐怖が心を朝霧のように包み込み、廊下はさらに深く、暗くなるのだった。
進む者と、待つ者。果たして、どちらが正しいのか、それともどちらも間違っているのか。わからないまま、ただ暗闇に飲み込まれていく。